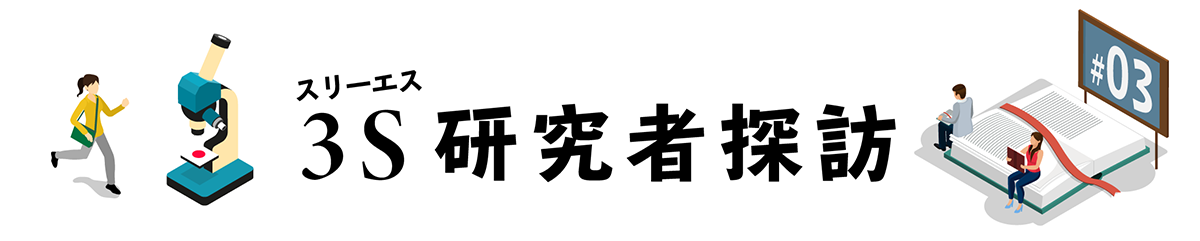
3S(スリーエス)とは、 稲盛研究助成 を受けた研究者から構成される「盛和スカラーズソサエティ(Seiwa Scholars Society)」の略称です。3Sでのつながりをきっかけにその多様な専門性の交流が深まることで、助成対象者の研究がさらに発展していくことを願い、1997年から活動してきました。連載「3S研究者探訪」では、さまざまな分野で活躍する、3Sの研究者へのインタビューをお届けしていきます。第3回は、京都大学の赤石大輔(あかいし・だいすけ)氏=2019年助成対象者=です。

京都大学の芦生研究林は、京都府北東部に広がる研究フィールドです。研究林は今後どうあるべきか。その持続可能性を検討するなかで赤石大輔特定助教は、自然環境だけでなく森を源流とする川の流域に広がる地域の暮らしをも対象とする必要性に気づきました。その結果、採用されたのが研究者と市民が協働して取り組む新しい研究スタイルです。工夫をこらして地域と関わりながら、着実に進めてきた研究の現状と課題、今後の展望などについてお話を伺いました。
森と里 その持続可能性は「連環」から生まれる
── 初めに芦生研究林の現状について教えてください。
赤石大輔氏(以下敬称略) 植物学者として知られた中井猛之進博士*1 は、かつて「植物ヲ學ブモノハ一度ハ京大ノ芦生演習林ヲ見ルベシ」と語りました。その理由は芦生の森の生物多様性にあります。研究林は由良川の源流域に位置し、暖温帯林と寒冷帯林の移行帯にあたります。そのため両方の気候帯の植物や動物が共生し、生物多様性に富むのです。ところが近年、鹿の過剰採食によって森林破壊が進み、多様性が損なわれています。この危機的状況をいかに食い止めるのか。これが我々の当初の問題意識でした。
── 「森里海(もりさとうみ)連環学」とは、どのような学問なのでしょうか。
赤石 森里海連環学は、京都大学の田中克教授によって2003年に提唱された新たな学問領域です。森から流れ出た川が里を経て海へと至る一連のつながりは、相互に関係しています。この連環をベースとして、持続可能な社会をめざした自然環境の価値と評価の基準と、それらを管理する社会の仕組みを考えるのです。芦生の原生林、ここから流れ出る由良川、流域にある美山町の人々、そして舞鶴湾がどのように連環しているか、また連環が途絶えているかといったことを考え明らかにすることです。我々はこのような森里海連環学の考え方を活かして由良川の流域全体を捉え、流域全体の持続可能性を高めたいと考えています。
── 流域全体の持続可能性を考えるとなると、研究対象がかなり広がりそうです。
赤石 その通りです。そもそも自然科学の取り組みだけで、社会を持続可能にすることはできないでしょう。だから田中先生も研究者にとどまることなく、問題意識を広く地域の方々と共有していかない限り、世界は変わらないとおっしゃっています。市民の皆さんが自分たちで考え、その結果を行動に移すきっかけとなるような研究者からの情報提供や対話を進めます。森里海連環学のこのような考えに基づき、私たちは様々な社会連携事業に取り組んでいます。
── 地域との連携重視について、どのように地域の方々と関わっておられるのでしょうか。
赤石 できる限り現地に赴き、地域の方と話すよう心がけています。コロナ禍のため今は少し途絶えがちですが、基本的に月に何回か現地に入り、1〜2泊して戻るスタイルで研究に取り組んでいます。現地では勉強会を開催して地域の方と交流したり、研究林に常駐している研究者と打ち合わせなどをしつつ研究を進めています。
── 研究グループには、どのようなメンバーが所属しているのでしょうか。
赤石 幅広い領域から多彩な研究者が集まっています。私自身は森林をフィールドとする生態学の研究者ですが、チームには経営学や心理学などの専門家も加わり、学際的な研究グループとして活動しています。例えば経営学の観点からは地域の観光資源を有効活用する観光ツーリズムを考え、生態学の観点から、ワサビや栃の実など地域の自然資源を持続可能な形で土産物などとして利用を検討するといった案配です。一方では心理学の先生に地域住民との関係構築のアドバイスを求めたり、共同で地域の実態についてのアンケート調査やヒアリングなどを行っています。

地域との連携の成果が絶滅種の再発見に
── 地域との関わりが大切とのことですが、研究林は美山の人たちからどのように受け止められていたのでしょうか?
赤石 正直なところ、近年は関係性がやや薄れつつありました。歴史を振り返ると、1921年に京都大学が芦生の森を借りたのは、教育・研究の場としての活用だけでなく、林業を行って大学の活動資金をまかなうためでした。当時は地域の人を雇用して植林し、木材の搬出や炭焼なども行っていたのです。ところが1960年代後半ぐらいから林業では採算が合わなくなり、縮小していきました。1990年代にダム建設の話が出たときには、大学と地域が連携して反対運動をしたこともあったようです。けれどもその後、次第に地域の方との交流が少なくなり、距離が少し開いてしまいました。
── 住民の方々からすれば、いろいろな思いを抱えておられそうですが……。
赤石 きっとそうだと思います。ですので、まずは地域の方に芦生や美山町への思いをお聞きするところから始めて、一緒に解決できる課題はないか考えました。もちろん、それだけはなく研究者だからこそ提供できる情報や、自分なりの専門性を活かして相手に有用と思ってもらえる話題を考えるといった工夫をしています。「芦生もりびと協会」*2 のガイドさんたちとの交流もその一環で、2018年から彼らと始めた取り組みが、最近一つの成果につながりました。それがキイロスッポンタケ*3 の再発見です。
── キイロスッポンタケ、ですか。
赤石 2019年から芦生研究林におけるキノコ相の調査を検討していました。芦生を案内するガイドさんたちも、ガイド中によく見かけるキノコについて学びたいというニーズがありました。そこで、より質の高いエコツアーを作ることと、研究林内でのキノコをモニタリングする「目」を増やすことの両立を目指した取り組みとして、7月にガイドさん向けに講習会を実施したのです。京都で絶滅種とされていたキイロスッポンタケについて紹介すると驚いたことに、ガイドさんの一人が「そのキノコなら、研究林の中で見かけたことがある」と。そこで2020年6月にガイドさんと一緒に現地調査を行い、キイロスッポンタケを48年ぶりに京都で発見し、その成果を論文にまとめたのです。芦生の森の豊かさの証明となるこのような発見をガイドさんとできたことに感激すると共に、市民と研究者の生物多様性モニタリングの新しい形が想像できました。

── その後、地域との交流はスムーズに進んでいるのでしょうか。
赤石 苦労しつつも着実に進めています。観光地として知られる美山では、すでにいくつもの団体が活動されています。そんな中で我々が後発で出ていっても、地域の方からすれば「今さら大学に何ができるのか」と疑問視されるのは当然の流れです。もとより我々の研究がお金儲けに直結するわけでもない。当初は「芦生の森は結局のところ、大学の森であり、地域からは遠い存在だ」という声もありました。
美山にはUターンやIターンで移住してきた若い人たちが、結構いらっしゃいます。30代から40代の比較的若い世代も多く、美山に強い魅力を感じています。そのような「自分たちの手で美山の魅力を広く発進していきたい」との思いを持っている方たちにアプローチしたところ、ぜひ一緒にやってみたいと話が転がり始めました。
地域住民と本音で語り共に学ぶ、新しい研究スタイル
── 話し合いのなかでどのようなことが見えてきたのでしょうか。
赤石 森の問題と里の問題は、持続可能性という点でお互いに密接にリンクしています。芦生研究林の持続可能性を考えた時、美山町地域の持続可能性も共に考えることで解決の道につながると考えました。美山はかやぶきの里として知られているものの、過疎化・高齢化の問題にさらされています。また平成の大合併により旧・美山町は南丹市の一部となりました。その結果、美山町単体であった時よりも意思決定に時間がかかるという部分があるようです。
地域の様々な主体、また個人が様々な課題を抱えている。その課題を共有し、お互いが手助けできることを見つけることで、解決の糸口を見つけることができないか。また我々研究者は地域と地域の外にある様々な主体とをつなぐ橋渡し役にもなれるのではないか、ということを考えました。
── 課題共有のためにどのような活動をされているのでしょう。
赤石 里の持続可能性に関しては、まず人々の暮らしが維持されなければなりません。自然資源を活用した取り組みが経済的に成り立つように考えるには、経営学の専門家に加わってもらうと同時に、地域の方々の率直な思いをぶつけてもらう必要があります。そこで対話の場づくりとして「美山×研究つながる集会」を立ち上げ、2020年の2月に第1回を開催しました。我々がこれまでの研究成果を地域の方々に報告すると同時に、美山の現在の課題を地域の方から直接伺う場です。また、このような上流域での問題を、都市部の多くの人に共有してもらおうと考え「京(みやこ)と森の学び舎」という市民講座を始めました。これには大阪や京都など都市部の方々に参加してもらい、芦生研究林や美山町を訪れ、現場で活動されている方々との交流を進めています。地域住民と研究者が共に学び合う地域学会としては、屋久島や対馬の先行事例が知られていますが、これらに習って例えば「美山ソサエティ」といった地域と研究者のプラットフォームを今後、育んでいきたいと考えています。


── 自治体、地域との協働に関して赤石先生は、石川県の能登でも以前いろいろ経験されていますね。
赤石 能登で9年間取り組んできた里山里海の保全事業では、大学と自治体、そしてNPOの連携により地域の自然環境保全と地域活性化を一つの流れに統合し、自治体の施策にまで落とし込むということができました。具体的には、石川県珠洲市の地域連携保全活動計画の策定に関わり、地域が一体となって取り組む行動計画を描くことができました。美山でも30代や40代の方々が集い、新しい活動を始めたいという話が出ていて、個人的にもサポートしていきたいと考えています。その際に、地域のそれぞれの活動と自治体施策との連動も地域での活動を後押しする一つの手段となります、それについては能登で経験済みなので、その際に得たノウハウを美山で活かしたいと思います。
── いずれにしても腰を据えた取り組みが必要ですね。
赤石 以前活動していた能登では、様々な活動が目に見える形で成果を出し始めるまでに7、8年かかりました。美山でも時間がかかるのは覚悟しています。それでも地域の方に支援いただいた結果、初年度に「つながる集会」のような対話の場をもつことができ、着実な一歩を踏み出せました。また、地域の元気な若い人たちと話し合いをしながら、物事を進めていける場を確立できた。この経験はとても励みになっています。芦生研究林は、今後も数十年単位で京都大学が管理し続けるので、長期的な視点でプランを進めていきたいと思っています。研究の進め方や成果の出し方について、美山では新しいスタイルでの挑戦を考えています。研究成果の社会還元について従来のスタイルをレベル1とすれば、これは研究そのものは研究者が行い、講演会などで研究成果を報告するやり方です。そこに近年はSNSなどを活用する市民参加型、例えば市民からアイデアを募ったり、気象関連などでは各地のデータを募ったりするスタイルが出てきました。これをレベル2と捉えています。
── では美山ではレベル2で進めていくのですか。
赤石 その一歩先、レベル3の展開に挑戦します。課題設定の段階から研究者と地域住民がともに考え、共に研究を進めるのです。レベル2よりもさらに深く、根源的なところから地域の方に関わっていただく、新しいスタイルです。実現するには、研究者である我々の思いを知っていただき、地域の方の思いも聞いた上で、お互いが共有できる思いを柱として打ち立てる必要があります。私自身も研究者としてだけでなく、様々な形で芦生や美山町に関わる意識で活動しています。こうした動きが、きっと自分の枠も広げてくれるはずです。

恩師に導かれ芦生へ
── そもそも研究者を目指したきっかけは何だったのでしょうか。
赤石 子どもの頃から研究者へのあこがれはありました。金沢大学で恩師の中村浩二先生*4 と出会い、生態学の道に進みました。その中村先生は京大出身で、まさに芦生で長年研究を続けてこられました。だから、自分では「先生が私を芦生に呼んでくれたんだな」と思っています。私を能登に導いてくれたのも中村先生で、その能登での経験が美山で活かされる。何か特別なめぐり合わせを感じます。
── ご自身の今後の研究の方向性、課題などをお聞かせください。
赤石 地球は今、6度目の大絶滅期に入ったのではないかと危惧しています。しかも過去の大絶滅との大きな違いが2つあります。一つは原因が人間の活動であること、もう一つは以前の大絶滅と比べてとても早いスピードで進んでいることです。そしてそのことが私たち人間にも大きな負の影響を及ぼすことが予想されます。この流れをなんとしても食い止めなければなりません。そのために何ができるのか。もちろん一人の力でできることなどたかが知れていますが、自分の足元から始める必要がある。だからこそ多くの人との協働が必要だと肝に銘じながら、日々活動に励んでいます。
── ありがとうございました。
*1. 明治~昭和期の植物分類学者、理学博士。東京帝大教授、小石川植物園長、ボゴール植物園長、国立科学博物館長などを歴任
*2. 地域のガイドツアー団体からなる一般社団法人。現在、4団体が所属。芦生研究林と協定をむすび、安全・環境に配慮した入林ルールのもと、ガイドツアーを実施している。芦生研究林内では、本協会の認定ガイドのみがガイドツアーを許可されている
*3. 学名:Phallus flavocostatus Kreisel。頭部は粘り気があり、強い匂いを放つ。この匂いにハエなどの虫が引き寄せられる。1972年に下鴨神社のシイの倒木から発生しているものが観察されたが、京都府レッドデータブックでは2002年度版から絶滅種として記載された。日本全土に分布し、海外では中国大陸、スリランカ、インドネシアにみられる
*4. 金沢大学名誉教授(農学博士)。石川県の里山里海の保全や総合的活用、地域再生に携わる。現・石川県立自然史資料館・館長
| いつもそばにあるもの |
 竹かご 山に調査に入るときには、必ず竹かごを背負う。「学生時代からの習慣ですから、もう20年近くになるでしょうか。キノコはとても柔らかく、リュックに入れると潰れてしまうので、竹かごにいれて大切に運んでいます。学生からはダサいと言われますが、山で仕事をする人から、どこのかごを使ってるの? と声をかけられて、話が弾むきっかけになります」 |
|---|---|
| この一冊 | 『アフリカの難民キャンプで暮らす – ブジュブラムでのフィールドワーク401日』小俣直彦・著 アフリカの難民問題について、著者が現地の難民キャンプに住みこんで行った調査が体験談としてまとめられている。「人々の暮らしの詳細な描写に引き込まれ、著者の研究手法が私と似ている点にも共感しました」 |
赤石 大輔(あかいし・だいすけ)
京都大学フィールド科学教育研究センター特定助教。1978年群馬県生まれ。金沢大学大学院自然科学研究科博士課程後期修了、博士(理学)。金沢大学・研究員、NPO法人能登半島おらっちゃの里山里海・研究員、珠洲市自然共生室・自然共生研究員を務める。域学連携事業の企画立案からNPOの設立・運営、多様な主体の連携による里山保全事業の計画策定など、研究者の枠を超えて様々な業務経験を積む。環境省・近畿環境パートナーシップオフィス勤務、京都大学森里海連環学教育研究ユニット特定助教を経て2020年より現職。
取材・文:竹林 篤実(チーム・パスカル)
*インタビューはオンラインにて実施しました
写真はすべて赤石氏提供
#01 梅津理恵氏デバイス革命の鍵を握るハーフメタルの電子を視る ─理論と応用の間をつなぐ基礎研究の底力─
#02 西浦博氏数理モデルで新型コロナの流行を分析、感染症との戦いの最前線 ─人々の行動変容までを関数に入れた感染症モデル化の試み─
